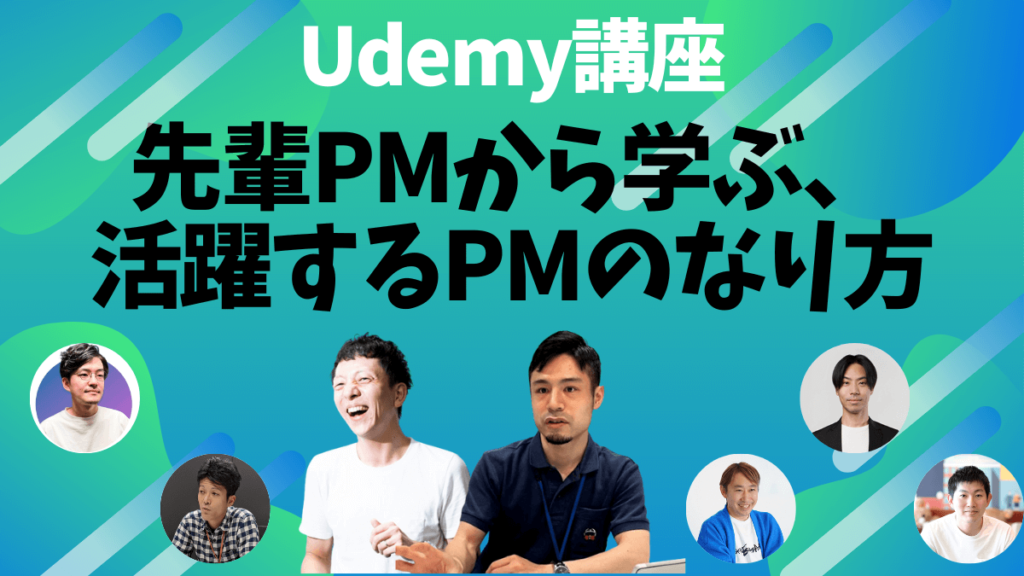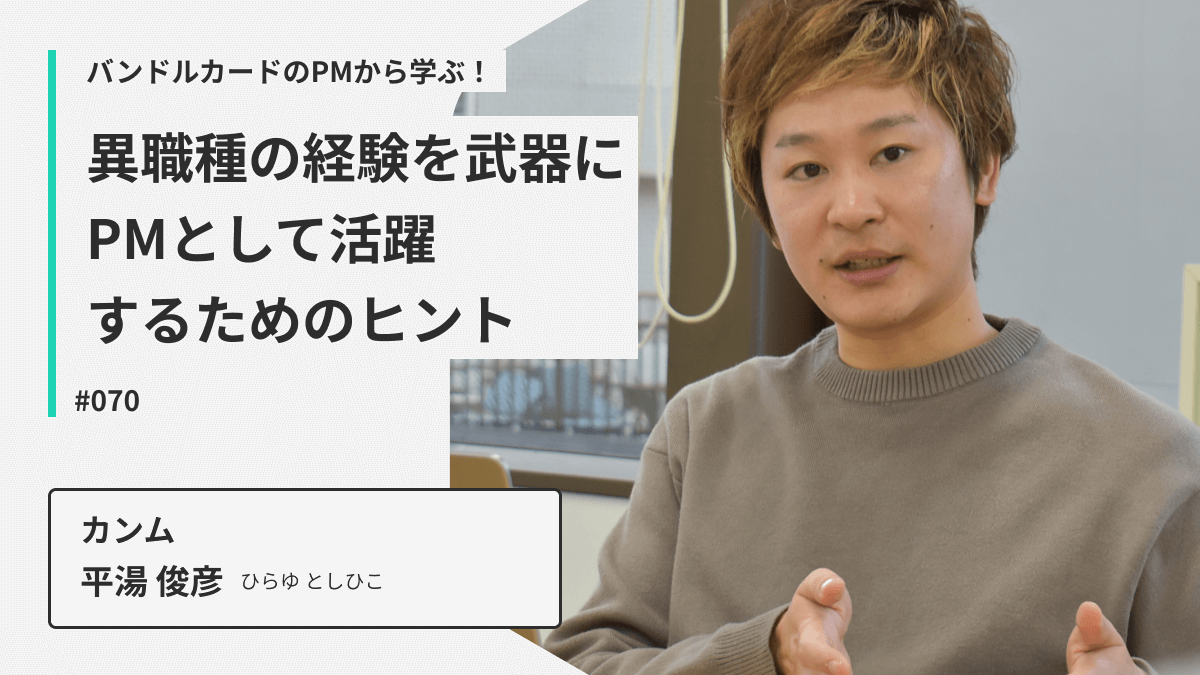
今回は、株式会社カンムでプロダクトマネージャー(以下、PM)を務める平湯 俊彦さん(@piyopiyo719)に仕事内容やキャリア、マイルールなどを伺いました。
平湯さんは、新卒で流通系クレジットカード会社に入社し、CSからマーケティング部門まで幅広く業務を経験した後、オペレーション構築・改善を強みに株式会社カンムに転職されました。業務改善や管理画面関連のプロジェクトを進める中で「売上を生み出したい」という熱意のもとPMに転身し、現在は「バンドルカード」のPMとして活躍中です。
直近では「ボーナスタウン」という新規サービス立ち上げを担当。立ち上げの裏話や、PMに興味を持った理由、過去の経験を強みにPMとして活躍するコツ、スキルアップのために取り組んだこと、「決める人間になる」というマイルールに込められた思いなど様々なお話をうかがいました。
これからPMを目指す方や、PMになったばかりの方は特に必読の内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。
目次
株式会社カンムにてバンドルカードのPMを担当
── まずはご自身の仕事について教えてください。
平湯:株式会社カンムにてバンドルカードというプロダクトのPMを担当しています。バンドルカードは最短1分で作れるVISAのプリペイドカードで、アプリをインストールして会員登録するとすぐにVISAのカードが発行されます。手軽にVISAカードを発行しネット決済できるという点がメリットです。また、希望者はプラスチックカードを発行して実店舗決済が可能です。さらに「ポチっとチャージ」という後払いチャージの手段もあり、家の中でVISAカードの発行からチャージ、買い物まで実現できるサービスを提供しています。
── 所属組織や関わっているプロジェクトについて教えてください。
平湯:現在、バンドルカードに携わるPMは2人のみなのでほとんどのプロジェクトに関わっており、プロダクト全体が業務範囲となっています。最近では新しくローンチされたサービスや、不正対策周りを担当しています。
カンムのバンドルカードプロダクト組織は4〜5つ程のチームで成り立っており、それぞれにPMが所属しているような状況です。現状、私は2つのチームに所属しており、もう一人のPMが3つチームに所属しそれぞれ異なる目標達成を目指しているような環境ですね。
── 経営レイヤーとPMはどのように関わっていらっしゃるのでしょうか?
平湯:基本的にチーム内での意思決定は尊重していただいているので、細かいところはほぼチーム内で決められます。ただ、最初の大きい方針やプロダクトロードマップなどに関しては週次で開催されるBtoC事業の定例会で進捗報告する中でフィードバックをもらうような形です。
サービスの安定稼働を提供しつつ、新たな価値提供を模索する
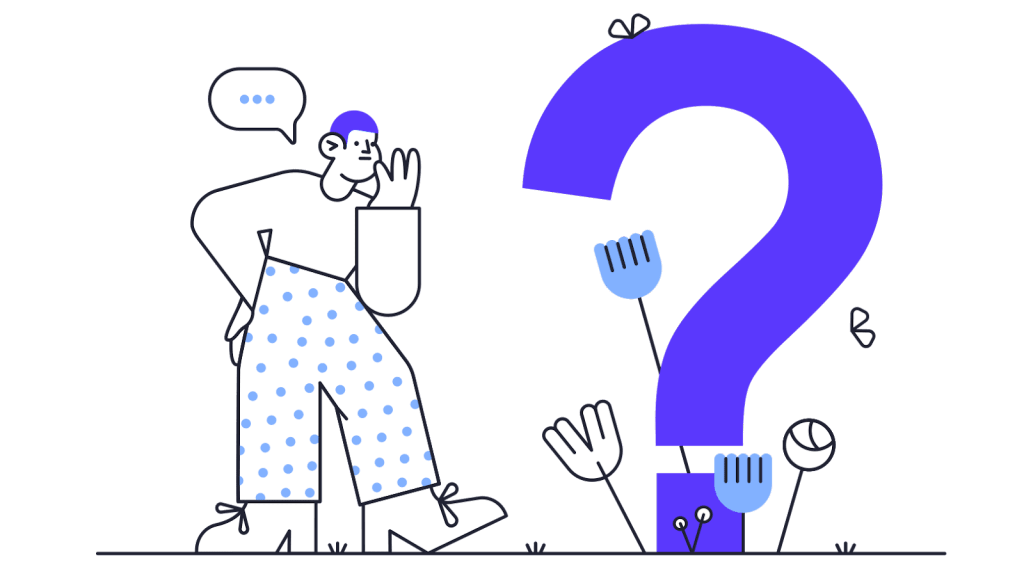
── バンドルカードのプロダクトビジョンについて教えていただけますでしょうか?
平湯:バンドルカードのプロダクトビジョンは絶賛構築中で、2025年の3月目処で設定する予定です。現状はサービスの安定稼働を経て、ユーザーに新たな価値を提供することを目標としている状況です。会社のビジョンは「お金の新しい選択肢をつくる」なので、プロダクトビジョンもここに沿ったものにはなるはずです。
そもそも、カンムにPM組織ができたのは1年前ほどで、それまでは組織としては存在せず、プロジェクトが先に存在していて、それをトップダウンに近い形でとにかく推し進めていた状況だったんです。今後はそこからさらに価値を提供していくために、チーム制でそれぞれがプロダクトをより良くしていくために考えるようなボトムアップ形式をとっていこうとしているので、まさに今プロダクトビジョンの重要性が高まっているフェーズになってきていると思います。
── プロダクトビジョンの構築とともに、チームの体制強化も進めている状況なのでしょうか?
平湯:そうですね。今までは経営層からプレイヤーへのトップダウンだったのですが、間にマネージャー層が入りました。さらに、その下に事業責任者やシニアPMが入る形で体制を作っている状況ですね。PM組織も絶賛拡大中で、先ほどご紹介したもう1名のPMも入社してまだ浅いです。今後も引き続き採用を検討していますので、気になる方はぜひご連絡ください!
── カンムにおけるミッションやプロダクトビジョンの方向性と、平湯さんご自身の価値観はどのように関連しているのでしょうか?
平湯:私は仕事にやりがいを求めたいタイプなので、貢献度の高い仕事ができるよう意識しています。端的に言うと、現在は「売上を作れる人間」になりたいと考えています。これは多くの企業で求められるスキルでもあり、今の職場ではそのための仕事をアサインしていただいていると感じています。
PMは企画段階からプロダクトをリードできるため、とても「手触り感」があると思っています。最近では、2024年11月に「ボーナスタウン」というサービスをリリースしました。クレジットカード会社のポイントモールをイメージしてもらえるとわかりやすいのですが、ユーザーのアクションによって広告やアフィリエイト収益を得るサービスです。カンムの新たな収益源として成長が期待される機能なのですが、プロジェクトの立ち上げからリリース、その後の改善まで担当しています。バンドルカード利用者の中でどれだけボーナスタウンを利用していただけるかで手数料の一部が我々の売上になる仕組みということもあり、施策の影響が直接売上に反映されるため「手触り感」を強く感じています。その中で、”プロジェクトマネージャー”から脱却し、”プロダクトマネージャー”として売上を作っていけるよう意識して取り組んでいます。
── プロジェクトマネージャーとして働かれていた期間は長いのですか?
平湯:キャリアパスの話にも繋がるのですが、もともとはCSやオペレーション領域での経験が長く、問い合わせ削減を目的としたUI改善や管理画面の改修を主に担当していました。プロジェクトを遂行する経験は一定積めたのですが、施策の目的は業務改善であり、「売上を作る」という点では見えてくる成果が異なっていました。売上創出の経験はいつか積んでおきたいと思っていた中、ありがたいことに、1年前PMを担当する機会をいただいたので「やるからには」と売上を作ることに注力して取り組んでいます。
── 「ボーナスタウン」はどのような流れで起案され、立ち上げまで至ったのでしょうか?
平湯:ボーナスタウンは既存の成功事例を参考に立ち上げが検討されました。もともと会社としての中長期計画の一環として位置づけられており、プロダクトロードマップでも構想されていた中で、私がアサインされ立ち上げがスタートした形です。既にバンドルカードという決済サービスを提供し、売上が立っている中で、そこに親和性のある形で展開するために、単純に導入するのではなく、さまざまな工夫を施す形でリリースしました。
個人的に、ボーナスタウンはアフィリエイト収益を上げるという点だけに留まらないと考えています。この基盤をもとに、さらなる成長のための手数料収入や広告収入の獲得などの幅広い展開が可能だと思っています。この辺りは自分で考えて動ける範囲かなと思いますし、リリースして終わりではないところに面白さがあると思っています。
ユーザーに「お得さ」「楽しさ」を提供するための基盤づくりがミッション
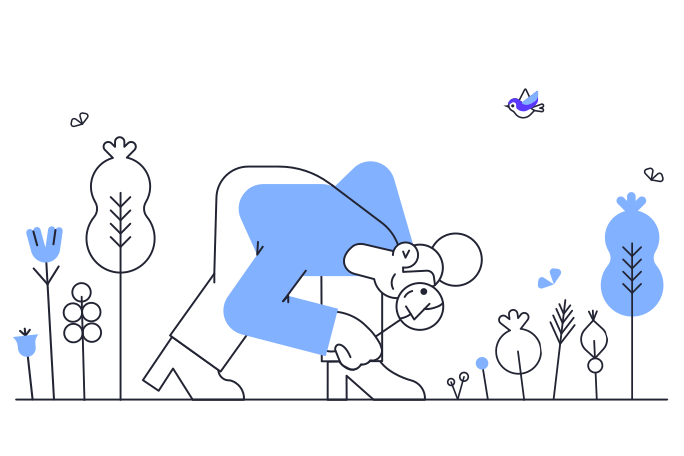
── 現在取り組まれているプロダクトの課題と現時点で考えている解決方法について教えてください。
平湯:私としてはユーザーに対し、いかに「お得さ」や「楽しさ」を提供していけるかどうかが課題だと思っています。バンドルカードは非常にシンプルでわかりやすい点が大きな魅力ですが、その上でサービスを利用することでさらなる価値を提供できればと考えています。解決策としてフックになってくるのは、やはりボーナスタウンだと思いますね。条件を満たすと残高を獲得できるような直接的なメリットだけではなく、金融全体に関わる困りごとに対しての解決方法を提供し「ここに行けば解決できる」という位置付けになることを目指して基盤づくりを進めている段階です。
その他にも、短期目線ではバンドルカード発行における本人確認(KYC)の体験向上も課題です。現状、KYCは多くの金融サービスで必要ですが、ユーザーにとっては非常に手間に感じる点だと思います。写真撮影を不要とする本人確認方法(eKYC)の導入などを行い、アプリ上だけで完結できるようなユーザー体験を実現することで解決していこうと考えています。
クレジットカード会社で経験したOPS領域を武器にカンムでPMに転向
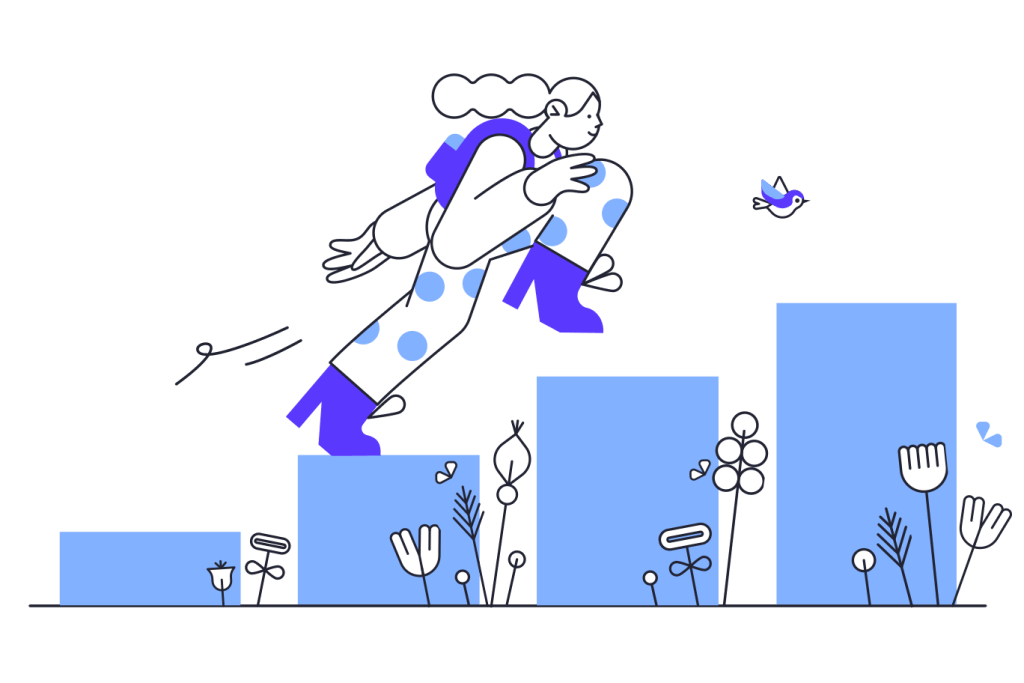
── 続いて、これまでのキャリアについて教えてください。
1社目(新卒):流通系クレジットカード会社
平湯:私は新卒で流通系クレジットカード会社に入社し、CS(カスタマーサポート)からマーケティング部門まで多岐に渡る業務を経験しました。電話応対や百貨店内でのカード入会手続き、利用促進キャンペーンの立案や運営、経営企画も担当しました。多くの業務を経験したのち、自分の強みは業務プロセスの構築や改善だと思うようになったんです。
2社目:ベンチャー企業のCS担当
その後、自分の業務プロセス改善スキルを活かしたいと思い、金融サービスを提供するベンチャー企業に転職し、業務プロセスの責任者としてフローの構築を担当していました。
3社目:株式会社カンム
そして、ご縁がありカンムに入社。CS体制の整備を行い、業務部長としてCSオペレーション領域の管理をしつつ、オペレーションリードとして複数のプロジェクトに参画するようになりました。オペレーション改善についてはプロジェクト化していたので、社内の開発メンバーと会話しつつリードマネジメントに近い業務領域を担当していましたね。そこから徐々にオペレーション以外のプロジェクトにも関与するようになり、リードを担うようになりました。最終的に、社内で新たにPM組織が立ち上がることになり、事業企画との二択で所属の選択肢をいただいたため、PM組織を選び現在に至ります。
PM組織を選んだ理由としては、先ほどお話したプロダクトマネジメントを通して「売上を作る」にチャレンジしたいという気持ちと、プロジェクト遂行の経験があったからですね。事業企画を選んだ場合、売上状況などに対して施策を練っていくマーケティング寄りの立場になっていたかと思いますが、プロダクトの成長や価値提供の観点からも意見を述べられる立場でいたい、という気持ちがあったのも大きな理由です。
── オペレーション領域から徐々に社内の開発メンバーを巻き込んだプロジェクトにも関わるようになったとのことですが、システム開発領域のコミュニケーションで困ることはありませんでしたか?
平湯:そうですね。当時の私の動き方としては一般的なプロジェクトリーダーとは異なっていたと思います。というのも、社内のエンジニアには優秀な方が多く、大まかな要求定義でも要件化し、実現してくれる方が多かったので、かなりそこに助けられていました。
ただ、自分自身システム開発領域のスキルアップには課題感を持っていましたね。私が業務部長を担当していた頃の上席の役員も元エンジニアの方だったので、フィードバックでもシステム要求定義やデータ連携まわりの要件定義も理解して進めた方が良いとご指摘いただいていました。自分でPythonやJavaScript(GAS)の学習を始め、簡単な業務効率化するシステムを自分で書けるようになって行きました。カンムはスキルアップを支援してくれる会社だったので、とても助けられました。月に1回「テックデイ」という機会があり、業務効率やスキルアップに繋がる物事に取り組んだ結果を発表する場があったんです。このあたりも活用してシステム周りの理解を深めていきました。
また、もともとカンムではデータの民主化が進んでおり、非エンジニアを含めた全社員がSQLを書けるんです。データ抽出基盤も整えてくれているので、エンジニアとの会話ではSQLで出した数値をベースに進めることができ、とても役立ちましたね。
── セールスやCSメンバーもSQLを書いて活用しているんですね…!
平湯:はい、全員書けます。開発以外の業務でも見たいデータってたくさんあるんですよね。例えば、先ほどご紹介した本人確認(KYC)の進捗状況などはステータスが全てデータベース化されているので、SQLで引っこ抜けば進捗率や確認にかかる時間などをダッシュボートに起こして確認できるんです。エンジニアさんに依頼せず自らモニタリングできますし、問題や課題も見つけやすくなるため全社的に活用しています。
SQLが全社に浸透しているお陰で、社内の様々な意思決定がデータドリブンでスムーズに行えますし、自分自身もPMとしてかなり活用しているため、早い段階で学べて本当によかったと思っています。
確実な要件定義とデリバリーを軸に、今後はUXデザインの領域を強化していく

── 続いて、12PMコンピテンシーを用いて、平湯さんのスキルや強みについて掘り下げていきたいと思います。まずは事前アンケートの回答内容を解説お願いします。
平湯:私はPMとしてのキャリアはまだ1年ほどで、全体的に自己評価は低めにしていますが、要件定義とデリバリーの領域は以前から意識的に取り組んできたところだと思っています。要求定義や要件定義に関しては、PMになる前から実現したいことを具体的な仕様に落とし込み、それがしっかりとプロダクトに反映されるように工夫していました。「デリバリー」については、PMとしてこれまでに2つのプロジェクトをリリースまでリードしましたが、リリースまでの準備やスケジュール管理の重要性、必要なステップがかなり掴めたと思っています。
── 要件定義やデリバリーにおいて、特に重要だと感じたポイントは何ですか?
平湯:足元の話にはなるのですが、やはり「スケジュール設定」と「ドキュメント管理」だと思っています。しっかりした計画を立て、スケジュールに落とし込み、それに沿って進行していくことは成功の鍵だと思っています。ドキュメント管理については、カンムはもともとドキュメント化する文化が根付いているので、当たり前にやっているものの、プロダクト要件定義書(PRD)は特に丁寧に作成・更新し、関係者間での合意形成を欠かさないようにしています。現在は、PRDのフォーマットが統一されておらず、シニアPMを含めてそれぞれが独自の形式で進めている状況です。今後体制強化を進める中で統一していくことになるかと思っていますが、現時点ではチーム全体で合意が取れることを重視して作成しています。
── ボーナスタウンをローンチする過程で、特に苦労された点やスキルのアップデートに繋がった経験を教えてください。
平湯:プロダクトストラテジーの部分で課題を感じましたね。ボーナスタウンは、最小限の機能でリリースすることを優先しましたが、とはいえ将来的なビジョンやプロダクトの方向性を会社のビジョンとどう接続していくかという点が大変でした。頭の中にはなんとなくイメージしているものの、実際に言語化して各ステークホルダーと握っていくのに苦労し、何度も代表の八巻さんと壁打ちを行い、フィードバックをもらいながら進めていきました。壁打ちの中では「プロジェクトにリソースを割く意味」や、「どうやって売上に繋げるのか」といった問いに答えるため、ユーザーに提供する価値を言語化し、事業計画として落とし込んでいきました。細かい開発アイテムについて議論するというよりも、抽象的な議論から具体的な仮説を立てていく形で「こんな施策があり得るよね」「こういう可能性があるよね」といった話から共通認識を作っていきました。いざ進めるとなった段階では改めて説明が必要になるかもしれませんが、基盤となる共通認識は形成できたと思います。
── ボーナスタウンのビジネスモデルや事業計画を策定していく中で、特に重要だった機能やポイントはどこだったのでしょうか?
平湯:ボーナスタウンの核となるのは、バンドルカードの仕組みを活かして「お得さ」をユーザーに提供する点です。バンドルカードはそもそもポイント制を持たない、チャージして使うタイプのカードですが、その中でユーザーが条件をクリアすると、残高が自動的にチャージされる仕組みを作りました。ユーザーが手間を最小限に、普段の行動を少し変えるだけで新しい価値を得られるかどうかが重要だったので、この辺りが事業計画上の売上目標にどう貢献するか、プロダクトの方向性としてどう位置づけていくのかを慎重に議論しました。結果的に、そのアイデアが事業計画と一致したのでリリースに至った形です。
── 今後、特に伸ばしていきたいスキルはありますか?
平湯:Customer Insightの領域、特にUXデザインに関わるスキルを伸ばしたいと思っています。個人的には開発と並行して企画をどんどん生み出しつつ、それをしっかり回していくことが大切だと思うのですが、自分がデザインができればよりテンポ良く回せると思うんですよね。データ分析や要求定義はある程度できてきていて、決済の仕組みもだいたい理解している中で、新しいプロセスを生み出そうとした時に、現場への業務影響などの勘所はつくのですが、UIやユーザー体験の設計などはまだ経験値が少ないと思っているので、これから伸ばしていきたいと思っています。
UXの観点からも、現在ユーザーインタビューを行い、そのフィードバックをプロダクトに反映させるプロセスを回しているのですが、インタビューの設計や結果の言語化、具体的な体験設計への落とし込みなどまだまだ学ぶべき点が多いなと思っています。
現在もデザイナーの採用を積極的に進めているので経験がある方がジョインいただけたら非常に助かります。
決める人間になり、最後までやり遂げること、コミュニケーションに気を配ることがマイルール
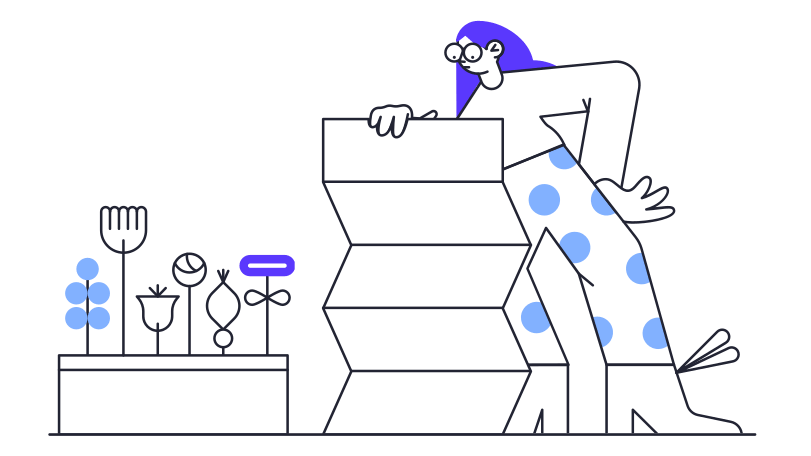
── 大切にしているマイルールを教えてください。
平湯:この質問をきっかけに改めて考えてみたのですが、3つあると気づきました。
1つ目は「決める人間になる」ということです。PMの役割は意思決定をすることだと考えています。たとえ状況が不透明であっても、自分の中でロジックを組み立て、意思決定をするのが重要だと思っています。
2つ目は「最後までやる」ということです。一度やると決めたからには、どんな障害があっても前に進む必要があります。もちろん、どうしても自分一人では進められない場合は、他の人の力を借りることも含め、最終的にやりきる覚悟を持っています。
最後は「コミュニケーションに気を配る」ことです。特に、チーム内でサプライズが起きないようにすることを心がけています。突然の変更や計画の不透明さがあると、メンバーが同じ方向を向けなくなってしまいます。そういった状況を防ぐためには、地道ですが定期的な情報共有やドキュメント作成を徹底しています。毎朝チーム内コミュニケーションを実施しているのですが、不在のメンバーがいる場合は別途時間を取って、情報共有の取りこぼしが発生しないようにしています。みんなで決めた目標や方向性がある中で、そこで違う話が出てきたりすると不安になると思うんですよね。そういった点が積み重なるとスピードが遅くなったり、お互いの要求に応えられなくなってきたりするので、このあたりは結構重視していると思います。
── コミュニケーションの重要性を意識するきっかけやエピソードなどがあれば教えていただけますか?
平湯:やはり実際にプロジェクトを進める中で経験したことが大きいと思います。進行する中で誰が何を考えてるかよくわからない状態になったんです。大枠では皆同じ方向を見ているものの、部分的に「なんで今それやる必要があるの?」とか「急になんでそれが降りてきたの?」といったすれ違いが出てきて、トップダウンとボトムアップの間に挟まれるような状況を経験しました。結果的にシニアPMに相談して立て直してもらったのですが、振り返るとしっかりポジションを取り、チーム側として上をしっかり説得する、またはその逆でステークホルダーからメンバーに直接降ろしてもらう機会を作るなどすべきでしたし、そもそも細かいコミニュケーションができていればこういったすれ違いは起こりづらかったのではと思っています。地道にコミニュケーションしていれば絶対起きないとは言い切れないですし、組織的な問題も絡んで来るかもしれないんですが、自分がやれることはやるべきだと思っています。
── 「決める人間になる」というマイルールは、どのような経験から生まれたのでしょうか?
平湯:これは、上司から教えてもらったことが大きいですね。PM組織ができたときに、入ってきてくれたシニアPMが育成経験もスキルも高く、一緒に働くことで学びがとても多かったんです。その方が一番仰っていたのが「PMは決める役割であり、決めたからにはやる」だったので、自然と重要性を認識しているのかなと思います。プロジェクトを進行していると「このタイミングで決めていいんだっけ?」という状況がちらほら起こると思います。リソースやスケジュールの関係で少ない情報量でも決めなきゃいけないシーンで自分の役割を認識し、同じ職種メンバーにも浸透していれば自信をもって決められると思います。また、組織全体で「PM=決める役割」であることを理解していれば、プロジェクトが失敗したとしてもフィードバックの方向性が変わってくると思うんです。決めたことに問題があったのではなく、決めるまでの情報収集方法や情報量に問題があったのでは、といった形で振り返りができます。自分自身もそっちの方が納得感がありますし、組織としてこういった考え方が浸透しているのはとてもやりやすいなと感じます。
チームの動きを見える化し、発言しやすい環境を整えることでいいチームをつくる
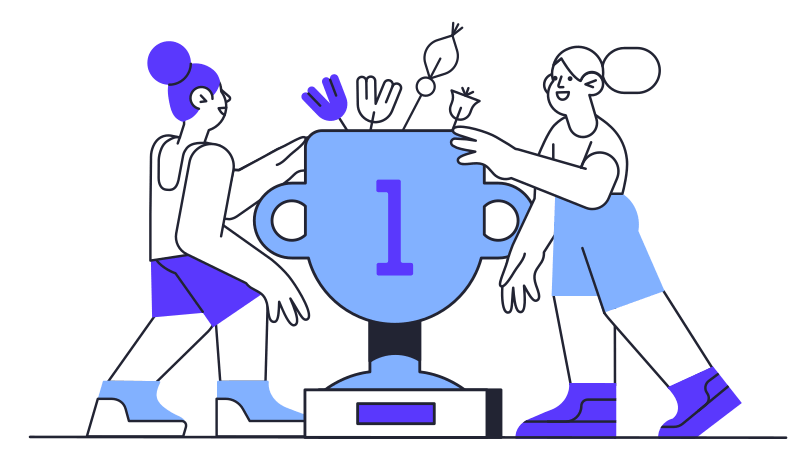
── いいチームを作るために工夫されていることはありますか?
平湯:地道なことだと思いますが、まず挙げるとすれば「見える化」ですね。今チームが何をしていて、どの課題を解決しようとしているのかを、明確にして見せるようにしています。施策や開発アイデアが並んでいる中で、なぜその優先順位なのかを伝えるためにも数値が重要だと思っています。ユーザーの遷移・離脱データといった細かいデータもチームメンバーには毎日の朝会で共有します。小さなことの積み重ねですが、これを続けることで、チーム全体の認識が揃い、意識が変わる手応えを感じています。
もう一つは、意見を言える環境をつくることです。事前に話したいテーマをドキュメントやチャットで共有し、考える時間を取ってもらうようにしています。アイデアを柔らかい段階でチームに投げてみることも多いですね。さらに、誰かが発言した際には必ずリアクションを返すなど、小さな工夫を大切にしています。
インプットを増やすこと、データ分析を怠らないことがいい企画のコツ

── 質の高い企画や課題に対して筋のいい打ち手を生み出すために、意識して取り組まれていることはありますか?
平湯:私が特に大事にしているのは、インプットを増やすことです。各領域で詳しい人は必ずいるので、積極的に聞きに行くことを意識しています。例えば、ボーナスタウンの施策を検討する中で、私はマーケティングやアフィリエイトの知見がないため、同じ事業やポイントモールを運営する方々に話を聞きにいっています。
話を聞く際は、直接的に数値目標や戦略を尋ねるのではなく、まずは仲良くなって自然な会話の中で知識を得るようにしています。現状、チームの中でこの辺りの事業内容や将来性については自分が一番詳しいと思っているのですが、これは直接話を聞きに行っているからかなと思います。
もう一つは、データ分析を怠らないことです。クエリを書いて積極的にデータを集め、それをもとに意思決定の材料として活用しています。この流れを一貫して自分でこなせるようになる、という点も工夫といえるかなと思います。
── 情報を持つ相手との接点やコミュニケーションで工夫されていることはありますか?
平湯:接点の作り方としては、商業相手として接触する場合が多いですね。問い合わせをすると、クライアントとして捉えてもらえるので、まずそこから話を聞きます。その後、さらに詳しい人を紹介してもらう形でネットワークを広げています。直接的な競合は紹介されませんが、実際に使っているお客様や関連分野の担当者などを教えてもらうことが多いです。
接点ができたら、まずはこちらの情報をオープンにすることを心がけています。「自分たちはこういう状況で、これが課題なのですが…」と先に話すことで、相手も構えずに話しやすくなると感じています。やはり普通に聞くと誰でも構えるので、そういった点は気を配っていますね。
平湯さんからのおすすめの本

── PMにおすすめの本がありましたらご紹介お願いします!
平湯:PMの基本的な役割や考え方を学ぶなら、やはりまずは「プロダクトマネジメントのすべて」かなと思います。この本は非常に読みやすいのですが、読み易すぎるが故に分かった気になってしまうかもしれないです(笑)実際に実践してみると、もっと深い思考が求められることに気づくのですが、全体像を理解するには適していると思います。
もう一つ、PMの役割を学ぶのにおすすめなのが『プロダクトマネジメントービルドトラップを避け、顧客に価値を届ける』です。この本はPM初心者にとって一番おすすめで、分厚すぎないので、重要なポイントを掴みやすいと思います。プロダクトが顧客にどのように価値を届けるのかを学ぶのに役立ちます。
また、企画や顧客理解に関する本では「ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム」や「たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング」がおすすめですね。ジョブ理論は顧客が解決したい課題に焦点を当てた内容で、非常に興味深いですし、実践 顧客起点マーケティングは、N1分析を起点にアイデアを見つけ出す具体的な手法が書かれています。この2冊はそれぞれアプローチが異なるものの、根底にある考え方は似ており、どちらも非常に学びの多い内容です。
最後に
平湯さんのお話はいかがでしたか?
感想や得られた気付き、気になったフレーズがありましたら、「#GrantyPM」を付けてツイートしてみてください!
先輩PMにオンライン相談できます!
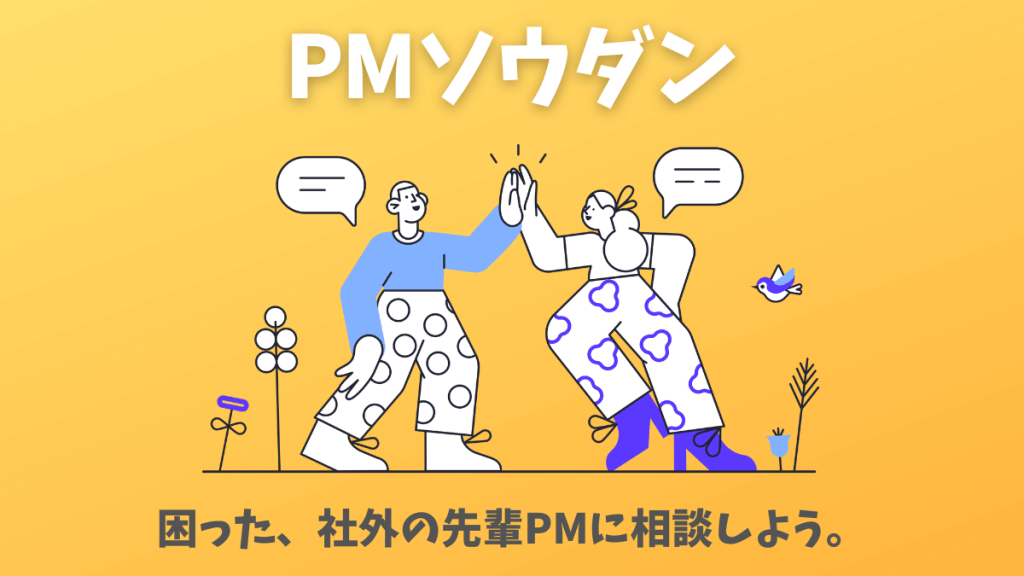
Granty PMでは、先輩PMにオンライン相談ができます!
素敵な先輩PMがたくさんいますので、こちらからぜひご覧ください!
PMインタビューの掲載企業・PMを募集中!

PMの業務やキャリア、思考を深掘りするインタビュー記事の掲載について、インタビュー内容など、詳細はこちらからご覧ください。
PM採用向けの広報にぜひご活用ください。