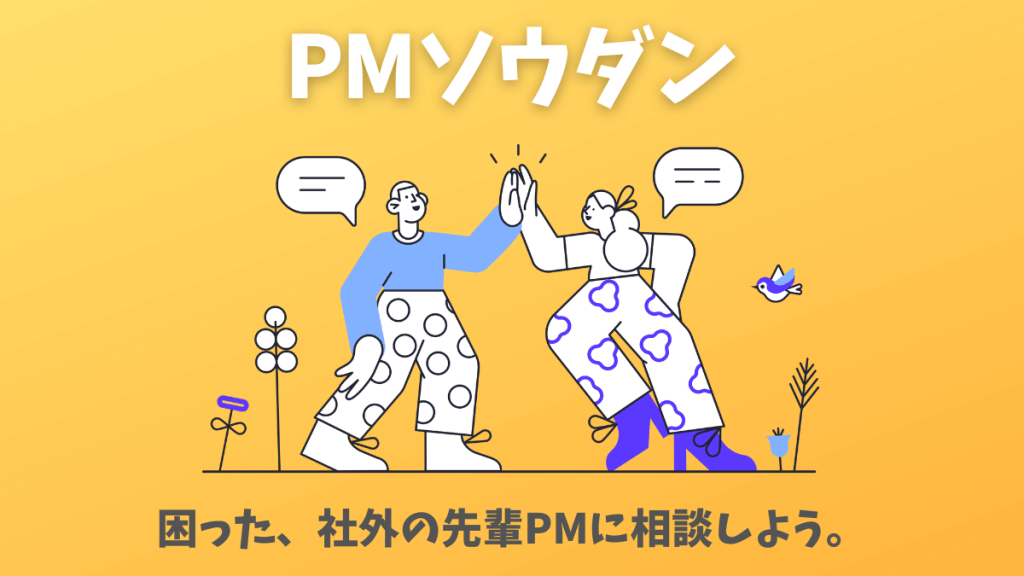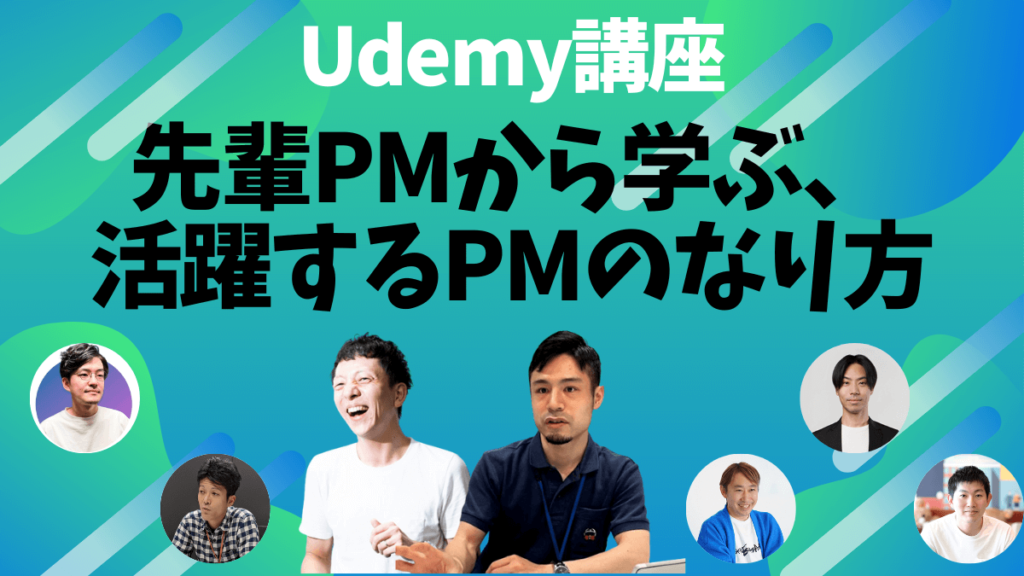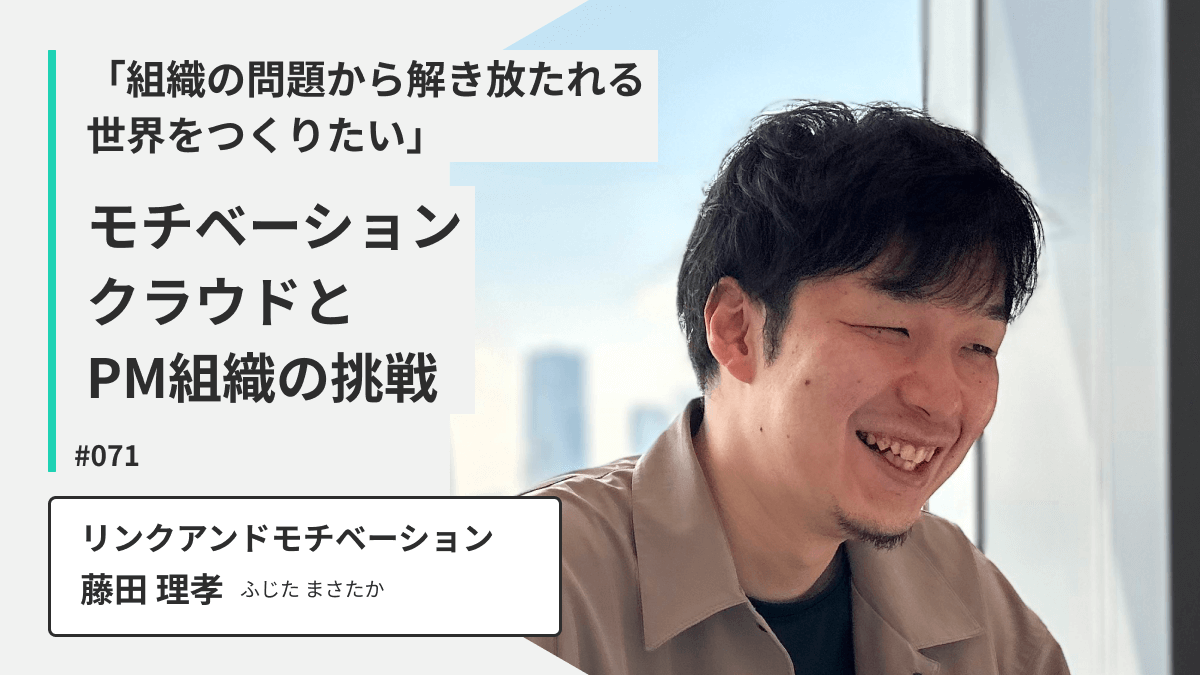
今回は、株式会社リンクアンドモチベーションでプロダクトマネジメント責任者を務める藤田 理孝さんにお話を伺いました。
「組織の問題から解き放たれる世界をつくりたい」
藤田さんは、そう力強く語ります。
新卒で同社に入社し、コンサルタントとして大企業からスタートアップまで幅広い組織変革を支援。その後、社内でジョブチェンジし、現在は「モチベーションクラウド」全体を統括する立場でプロダクトマネジメントに取り組まれています。
本記事では、
- 業績や知名度だけでは測れない「良い会社」の新たな定義
- 生成AIを活用した組織課題のパーソナライゼーション
- 「関係者の重心を重ねる」という独自のマネジメント哲学
など、プロダクトのビジョンからチーム運営のリアルまで深掘りしました。
「組織変革の民主化」という壮大なテーマに挑む藤田さんの言葉は、多くのプロダクトマネージャーにとって共感や気づきのきっかけになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
目次
① 自己紹介
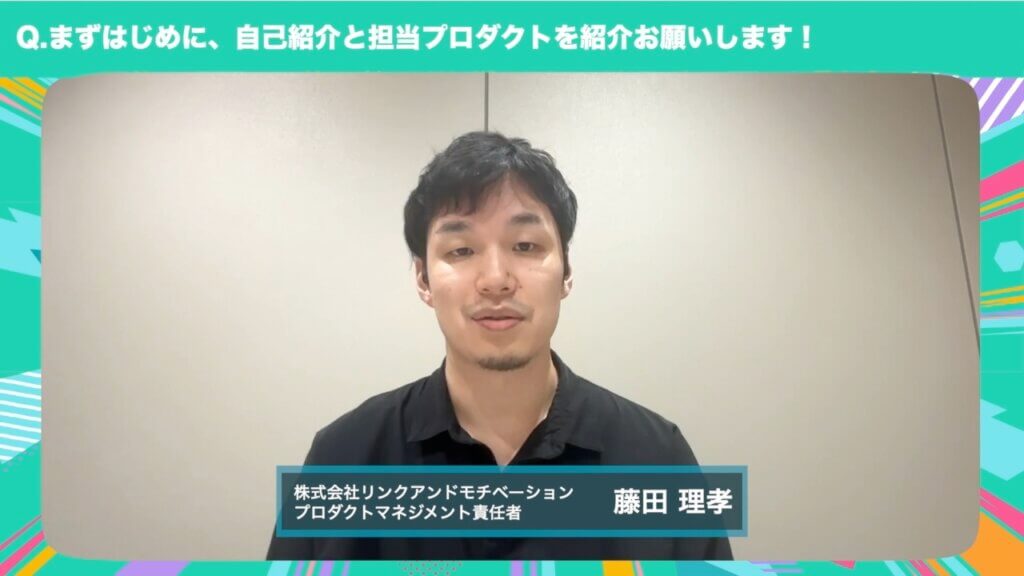
── まずはじめに、自己紹介と担当プロダクトを紹介お願いします!
藤田と申します。リンクアンドモチベーションでプロダクトマネジメント全体を統括しています。
当社では「モチベーションクラウド」という、組織の診断・改善を支援するクラウドサービスを展開しています。社員一人ひとりが自分の職場や会社の状態を理解し、より良い組織をつくるためのプロダクトです。
国内で100万人以上のユーザーにご利用いただいていて、北は北海道から南は沖縄の離島まで、全国の企業に導入されています。
モチベーションクラウドのシリーズには、エンゲージメント領域やマネージャー育成領域など複数のプロダクトがありますが、大きな括りとしては「モチベーションクラウド」としてご認識いただければと思います。私はその全体を横断してマネジメントしています。
② プロダクトのビジョンや対峙する課題、3年後の未来について

── 業界で「おかしいと思う当たり前」や「もっと良くなる余白」があるとすれば?
世の中の「良い会社」が主に業績や知名度で定義されていることです。それだけで本当に良い会社と言えるのでしょうか。
私たちは、業績や知名度だけでなく、働いている人の”働きがい”そのものが成長エンジンになっている職場も「良い会社」として評価されるべきだと考えています。
分かりやすい例で言えば、就職活動の人気企業ランキングです。知名度のあるBtoC企業や歴史ある大企業が上位を占めますが、働いている人にとっての「良い会社」は他にもあるはずです。もっと多面的な軸で良い会社が評価される社会を実現していきたいです。
── モチベーションクラウドが破壊したい”不公平”とは?
所属する組織によって働きがいを感じられる人と感じられない人がいる。これは誰かが悪いのではなく、働きがいを高めるためのノウハウや手法がまだ広く行き渡っていないことが本質的な課題だと考えています。
誰もが働きがいを感じ、素晴らしい仲間と一緒に熱中して働ける世界をつくりたい。それがモチベーションクラウドで実現したい未来です。
── この課題に初めて胸が高鳴った瞬間は?
コンサルタントとして企業支援を行う中で、職場の人間関係や仕事の楽しさを見いだせないことで悩む人が多いことを実感しました。
ただ、逆の瞬間もありました。支援がうまくいったり、モチベーションクラウドを活用いただいたことで、「自分のチームを自慢したい!そのくらいチームが変わったんです!」とおっしゃる方がいたんです。その変化を目の前で見たときに、もっと広げなければならないと強く思いました。
働きがいや仲間との関係性は人生の深い部分に直結している。そこにアプローチできることに、大きなやりがいを感じています。
── 生成AIの登場は、プロダクトにどんな影響を与えていますか?
私たちがアプローチしているのは、オペレーションというよりリレーションに関するものです。人間関係には無限の組み合わせがあり、AさんとBさんの間にしか生まれない問題が存在します。
極端に言えば、どうやって究極のパーソナライズを実現するか。業界や業種といった事業内容の違い、職種や仕事内容などの業務の違い、さらにはそれぞれの組織の体制やコンディションといった違いまでを正しく抽出し、完全な個別対応を実現することこそが、プロダクトの至上命題だと思っています。
今、モチベーションクラウドには100万人以上のユーザーがいらっしゃいます。それぞれ独自のコンテキストや文化をお持ちなので、個別対応できる幅が無限に広がったという意味で、生成AIの登場は追い風だと感じています。
また、組織診断の結果の解釈も、これまでは一般化せざるを得ない部分が多くありました。しかし、AIを活用することで、各部署に合わせたより具体的で個別性の高い情報提供ができるようになりました。今後は、組織状態が悪くなってしまう前に、その予兆を検知することも可能になります。
加えて、自然言語が使えるようになったことも大きいです。組織の領域って、突き詰めると正しさよりも納得感の方が重要なんですよね。自然言語でコミュニケーションできることは、プロダクトとして大きな革新だと考えています。
── 3年後、ユーザーの日常はどう変わっていますか?
私たちは「組織変革の民主化」と呼んでいます。組織の問題は誰にとっても身近ですが、良いチームのつくり方を教わる機会はほとんどありません。そのせいで、本来集中すべき仕事や顧客への価値提供が妨げられてしまうことが多いんです。
3年後には、モチベーションクラウドを使えば「組織の問題から解き放たれる」状態を実現したいと考えています。少し欲張りかもしれませんが、それくらいの変化を起こしたいですね。
── 他社ではなく自社でなければ解決できない理由は?
大きく3つあります。
1つ目は、20年以上のコンサルティング経験から得た知見をプロダクトに統合していること。
当社は2000年に創業し、組織変革のコンサルティングを行ってきました。25年間を通じて、お客様の組織に深く入り込みながら得られた知見をもとにプロダクトをつくっています。プロダクトのデータだけでなく、コンサルティングで培った新たな事例やナレッジを統合できることが強みです。
2つ目は、クラウドだけでなくコンサルティングやアウトソースも含めて支援し、深い関係性と膨大なデータを持っていること。
プロダクトだけでは解決が難しい問題はコンサルティングやアウトソースといった手段も講じながらご支援しています。ありがたいことに、お客様との関係性が大変良好なので、様々なアプローチで課題解決に取り組むことができています。
3つ目は、新しい挑戦を柔軟に受け入れるカルチャーです。
自組織のエンゲージメント向上に注力していることもあり、部門間の衝突がほぼありません。新たな挑戦においても、すごく柔軟に対応できるカルチャーがあります。
開発を進める中で、やりたいことを提案して反対されることはほぼなく、「お客様のためになるのであれば、やってみよう!」と背中を押してもらえます。経営陣に止められたことも一度もなく、常に建設的な議論ができています。
── 解決に向けた現状のイシューは?
ユーザーの多様性が急速に広がっているため、エンタープライズ特有のオペレーションや文化への適応はまだまだ発展途上です。日本発のSaaSで真にエンタープライズにフィットした事例は極めて少なく、その壁を越えることを本気で目指しています。
さらに、今後はマネージャーや部署長が自分の組織を改善できるよう、より深くオペレーションに入り込む必要があります。そのため、今後プロダクト数を大幅に増やしたいと考えています。
人事の方の管理・運用業務を楽にするだけではなく、現場の皆さんの使い勝手が良くなるように、HR領域全体を再編集しなければならないと思っています。目標設定、評価、ストレスチェックなど、さまざまなサービスを現場視点で再構築していきたいですね。
また、M&Aも積極的に進めていて、直近ではUnipos株式会社をグループに迎え入れました。自前でつくる以外の方法も含めて、プロダクトを増やし、統合していくことも大きなテーマです。
ただし現状は人員がまだまだ足りておらず、新たな仲間を全力で探しています。
③ 個人のキャリアや考え方について

── これまでのキャリアを教えてください。
新卒でリンクアンドモチベーションに入社し、最初はコンサルタントとして大企業やIPO前後の企業を支援しました。人事制度の設計やカルチャー変革など、組織戦略を扱う仕事を中心に約5年間取り組みました。
その中で、一つの会社と長期的に伴走するプロジェクトがありました。IPOに向けて人事制度を整えたり、企業統合に合わせてカルチャーを一新したり、新卒採用を強化したり。組織戦略全体をご支援する中で、土台となるエンゲージメントの計測にモチベーションクラウドを活用していました。
その後、社内でジョブチェンジし、プロダクトマネージャーとして開発に携わるようになりました。新規プロダクトの立ち上げや、停滞していたプロダクトの立て直しを経験しながら、徐々に管掌範囲を広げ、現在はモチベーションクラウド全体を統括しています。
── コンサルタントからプロダクトマネージャーへの転向で、活きた経験と苦労したポイントは?
ドメイン知識はコンサルタント時代の経験がそのまま活きました。また、クライアントの経営陣の方々との仕事も多かったので、ステークホルダーマネジメントやビジネスサイドへの知見も活かすことができました。
逆に、テクノロジーやシステム思考は真逆の世界でした。コンサルティングは属人性の高い仕事なので、そこは頭を切り替えてアップデートする必要がありました。
最初のアサインは新規プロダクトの立ち上げで、ドメイン理解やビジネスサイドの理解をそのまま活かせる役割でした。開発に詳しいメンバーとタッグを組みながら進め、リリース後は別のプロダクトのマネジメントを一任されました。
そこで一通りの仕事を経験し、その後は管掌するプロダクト数を順番に増やしていって、現在に至ります。レイヤーとしてはマネジメント方向に進んでいる感じですね。
── 強みとされている「マネージングアップ(上司や経営層への働きかけや巻き込み)」はどのように磨かれましたか?
プロダクトマネージャーの仕事は翻訳に近いと思っています。職種やレイヤーごとに重視する観点が異なるので、相手の言葉に翻訳して伝えることが不可欠です。
この力を養ったのは、自分で予算やリソースを獲得する経験でした。
例えばシンプルなモデルで考えてみると、会社経営では時価総額が一番上位の指標にあり、BS、PL、North Star Metric、開発アウトカム、Four Keysといったラダーが存在します。機能改善の話だけをしていると見落としてしまう観点や指標が、別職種や別レイヤーの方にはあるんです。
自分のプロジェクトが「いくら投資してどんなインパクトを出すのか」を説明責任を背負って語る。そのトライを繰り返す中で、経営から現場までのレイヤーを自在に行き来できる感覚が培われました。
コンサルタント時代の経験も大きかったと思います。人事担当の方、人事役員の方、経営者の方など、それぞれ関心ごとや優先順位が違っていたので、BtoBのクライアントワークは貴重な経験でした。
── 大切にしている行動指針やマイルールは?
「関係者の重心を重ねること」です。
少し極端な表現になりますが、「モチベーションがあるかないか」ですべてが決まるケースも少なくないと考えています。新規事業の立ち上げや、既存プロジェクトの進行、開発チームの関係性改善など、どんな場面でも同じです。そこにいる人がやりたいと自分の重心が乗っていることは前に進みますし、誰かの重心が乗っていないと、そこを起点に問題が起きたり、思うような出力が出なくなってしまいます。
なので、どんなプロジェクトを進めるときにも、「それぞれの重心が今どこにあるのか」を正しく捉え、それらが重なる点をうまく見いだすことが、仕事を円滑に進める一番の鍵だと思っています。
責任を明確にすることも大事ですが、それは重なった重心が変な動き方をしないようにするためです。ノイズが発生しないように注意しながら、役割を設計することがポイントです。
大事なことは、全員の認識が揃っていて、重心が重なっている状態をうまく実現できるかだと思います。
── チームで重心を重ねるために工夫していることは?
これに関しては、相互理解に尽きると思います。
相互理解も各レイヤーでどの程度できているかによって、重心の重なり度合いが変わります。「今、何の仕事をしているのか」というタスクレベルの相互理解もあれば、「何のためにこの仕事をしたいのか」という目的レイヤーの相互理解、「なぜこの会社で仕事をしているのか」というキャリアレイヤーでの相互理解もあります。
これが深いほど重心は重なりやすいので、特に大きなプロジェクトほど、深いレイヤーでの相互理解を大事にしています。立ち上げ直後など、プロジェクト初期に取り組むことを意識して全体を設計しています。
人数が多い場合は、オフサイトで合宿を行ったり、少数の場合であれば、直接声をかけて対話するだけでも効果があります。最初は効率が落ちているように思えるのですが、そこに時間を使った方が後々のズレが減るので、費用対効果も高いと感じています。
AIは様々なコンテキストを与えた方が話が早いですが、人間でも同じことが起こります。自分が持っているコンテキストは、なるべく早く開示してしまった方が、プロンプトに対する出力の精度が上がります。
当社では、新しい方が入社されたときも、パフォーマンスを出すよりも前に、組織の中で相互理解が深まることの方がはるかに重要であると信じているので、相互理解を促進するオンボーディングプログラムに非常に力を入れています。
── プロダクトマネージャーの採用について、未経験者をどう捉えていますか?
経験があるに越したことはないですが、プロダクトマネージャーという職種自体もほんの数年前に生まれたラベルですよね。今後も役割や職種は流動的に変わっていくと予想しています。
なので、今までの方法が、そのまま今後のプロダクトマネジメントに活きるとも思っていません。
一番大事なのは、新しいものへの適応力やアンラーンする力、不確実なものと向き合うタフネスだと考えています。
当社も新卒でプロダクトマネージャーに配属して、現在では大きなプロダクトを任せているメンバーもいます。シニアかジュニアかというよりは、もともとの素養の方が重視されるべきじゃないかなと思います。
── PMにおすすめの本はありますか?
ユニクロの柳井正さんの『経営者になるためのノート』です。
もともと次世代経営者育成のための社内用教材が出版されたもので、バイブルとして定期的に読み返しています。
プロダクトマネージャーをやっていると、これは本当に自分の仕事なのかと思うようなことや、何のためにやっているのか分からなくなる瞬間もたくさんあると思います。
この本には、傑出した経営者の方から、会社経営や事業運営、プロダクトづくりがどのように見えているのかが書かれています。
素晴らしいのは、すごくシンプルなことが書かれているんですけど、それをちゃんと実行することこそが難しいんだよな、という気付きを与えてくれる点です。
私はクオーター末に一度は必ず読み、自分が今足りていないところを明らかにして、次のクオーターの行動計画に反映するようにしています。
④ 読者へのメッセージ

── 最後に、記事を読んでいる方へメッセージをお願いします!
私たちは「問題の解き方」もそうですが、「解いている問題の面白さや意義深さ」にこだわりを持っている会社です。
働き方や組織の関係性というのはとても意義深く、挑戦のしがいがあるテーマです。そこに対して愛情を持って取り組んでいる方がとても多いチームだと感じています。
少しでも共感していただけた方がいれば、ぜひ一緒に挑戦したいと思っています。
リンクアンドモチベーションで一緒に働きませんか?
藤田さんが語ってくださった「組織の問題から解き放たれる世界をつくりたい」というビジョンに共感した方へ。
現在、当社が運営する求人サイト Granty には、リンクアンドモチベーション社の プロダクトマネージャー募集 が掲載されています。
👉 求人詳細はこちら
「組織変革の民主化」という壮大なテーマに挑みたい方、プロダクトを通じて働き方をアップデートしたい方は、ぜひチェックしてみてください。
まとめと皆さんへのお願い
藤田さんのお話からは、プロダクトを通じて「組織変革の民主化」を実現しようとする強い意志と、プロダクトマネージャーとしての具体的な実践知を感じることができました。
特に印象的だったのは「関係者の重心を重ねる」という独自のマネジメント哲学。単に役割や責任を明確にするだけではなく、メンバー一人ひとりのモチベーションを理解し、それを重ね合わせることがプロジェクト成功の鍵になるという視点は、多くのPMにとって示唆に富むものではないでしょうか。
また、生成AIの登場を「無限の個別対応を可能にする追い風」と捉え、組織課題のパーソナライゼーションに活かそうとする姿勢や、プロダクトマネージャーの本質的な素養として「新しいものへの適応力」「不確実なものと向き合うタフネス」を挙げられた点も、これからのPM像を考える上で重要な指摘だと感じました。
この記事を読んで「気づきがあった」「共感した」「このフレーズをチームで共有したい」と思った方は、ぜひ 「#GrantyPM」 をつけてSNSで感想をシェアしていただけると嬉しいです。あなたの一言が、他のPMにとっての学びや励みにつながります。